伽藍岳
がらんだけ
別府温泉の熱源域と考えられている伽藍岳は、鶴見火山群の北端に位置し、「鶴見岳・伽藍岳」として活火山に認定されています。標高1045m、またの名を硫黄山と言います。主な噴出溶岩は粘性の高い角閃石安山岩で、山頂部は2つの溶岩ドーム(溶岩円頂丘)に分かれ、南西斜面は径300mほどの円弧状の崩壊地形になっています。崩壊地の内側には、過熱蒸気(120℃)を含む活発な噴気活動が見られます。また、強い酸性(pH 1~2)の温泉水が湧き出しており、その一部は塚原温泉の源泉に使われて、多くの入浴客に親しまれています。
活発な地熱・温泉活動によって、岩石類は激しく変質し、金属成分を失って白色化した珪酸白土は、1990年代の初め頃まで別府白土として採取されていました。その鉱山跡の噴気地に、1995年7月頃から熱泥を噴き上げる「泥火山」が出現しました。写真は、1996年3月17日の泥火山と周辺の様子です。近頃の泥火山の状態は、いくつかの外部サイトに公開されています。

別府白土鉱山跡に出現した泥火山:直径約10メートル(1996年3月17日撮影) |
画面上方のゴツゴツした黒色の物は安山岩の転石です。下半分の白っぽい色は別府白土の名残りで、珪酸(SiO2)を主成分としています。その中にあって、泥火山とその奥の地層の一部は青っぽい色をしていますが、明礬温泉で言われる青粘土(ぎち;湯の花の原料)と類似のものです。実際、この周辺には天然の湯の花が見られます。塚原温泉の代表的な泉質は「酸性-含鉄(Ⅱ,Ⅲ)-アルミニウム-硫酸塩泉」という極めてユニークなもので、天然の湯の花の産物と言えるでしょう。
伽藍岳が別府温泉の熱源域とされるのは、次のような理由からです。
| (1) |
この地域で最も活発な地熱・温泉活動がある。 |
| (2) |
地理的にも地下水理的にも、別府温泉の上流部に当る。 |
| (3) |
別府温泉における地温の水平分布は、温泉水が伽藍岳方向から流れてきていることを示唆している。(別府八湯を参照) |
| (4) |
伽藍岳の地下約5000mの深さに、マグマ性流体の上昇を示唆する、電気抵抗が非常に低い領域が存在する。 |
(

由佐悠紀)
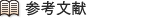
NEDO(1989):昭和63年度全国地熱資源総合調査(第3次)鶴見岳地域 比抵抗調査報告書(要旨).
竹村恵二・由佐悠紀・馬渡秀夫(1994):別府地域の火山岩調査(2)-北部地域-,大分県温泉調査研究会報告,45,11-14.
由佐悠紀・大沢信二・北岡豪一・竹村恵二・福田洋一(1995):伽藍岳の地熱調査,大分県温泉調査研究会報告,46,5-13.
大沢信二・大上和敏・由佐悠紀(1996):1995年伽藍岳塚原鉱山跡に出現した泥火山,火山,41,103-106.
